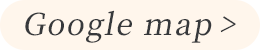こんにちは。長崎県諫早市にある歯医者「諫早ふじた歯科・矯正歯科」です。

歯を磨いているときや食事をしているときにふと、歯がぐらぐらすると感じたことはありませんか。そんな違和感を覚えたとき、まず疑ってほしいのが歯周病です。
歯がぐらつく原因はさまざまですが、大人になってから歯を失う最も大きな理由が、歯周病であることをご存じでしょうか。日本では成人の約8割が歯周病を抱えているとされており、自覚症状が出るころには病状が進行しているケースも少なくありません。
歯周病によるぐらつきを放置していると、最終的には歯を抜かなくてはならなくなる恐れもあるため、早期の対応がとても大切です。
この記事では、歯周病の基礎知識から歯がぐらつく原因、具体的な治療法、そして日常生活でできる予防法まで、詳しく解説します。健康な歯を守るための第一歩を一緒に踏み出しましょう。
目次
歯周病とは

歯周病とは、歯と歯ぐきの境目にたまった歯垢(プラーク)に含まれる細菌によって、歯ぐきや歯を支える骨が炎症を起こす病気です。初期段階の歯周病は歯肉炎と呼ばれ、歯ぐきが赤く腫れたり歯磨きの際に出血したりします。
進行すると歯周炎となり、歯を支える骨(歯槽骨)が徐々に破壊されていきます。この段階になると、歯ぐきが下がったり歯がぐらついたりといった症状が現れ、最終的には歯が抜け落ちることもあります。
歯周病の怖い点は、自覚症状が少ないまま進行することです。痛みがないからといって放置していると、ある日突然、歯が抜けそうと気づくことになりかねません。
また、歯周病は口の中だけではなく、全身の健康とも深い関わりがあります。近年の研究では、歯周病が糖尿病や心臓病、脳卒中、さらには妊娠トラブルとも関連があることが明らかになっています。
つまり、歯周病は単なる口の病気ではなく、全身の健康リスクを高める要因にもなり得るのです。
なぜ歯周病で歯がぐらつくのか

歯周病が悪化すると、歯がしっかりと固定されず、揺れてくることがあります。
しかし、なぜ歯ぐきのトラブルが歯のぐらつきという形で現れるのでしょうか。この章では、その仕組みをわかりやすく解説し、歯の動揺が起こる原因をご紹介します。
歯を支える組織が壊される
私たちの歯は歯ぐきだけに支えられているわけではありません。歯ぐき(歯肉)や歯槽骨、歯根膜などの歯周組織によって支えられることで、安定しています。それぞれが連携することで歯を正常な位置に保っているのです。
しかし、歯周病が進行すると、細菌が歯周組織に炎症を起こし、歯を支える骨(歯槽骨)を溶かしていきます。骨の量が減ると歯を支える力が弱まり、結果として歯がぐらつくようになります。
歯周ポケットが深くなる
歯周病の進行にともなって、歯と歯ぐきの間には歯周ポケットと呼ばれるすき間が広がっていきます。歯周ポケットの中に歯垢や歯石がたまり、炎症を悪化させる原因となります。
歯周ポケットが深くなるにつれて歯ぐきと歯の結合がゆるみ、歯の安定性も次第に失われていくのです。
歯周病によって歯がぐらつくときの治療法

歯がぐらぐらしていると、日常生活にも支障が出てきます。「もう歯を抜くしかないのでは?」と不安になるかもしれませんが、適切な治療を受ければ歯を残せる可能性も十分にあります。
ここでは、歯周病によって歯がぐらついた場合にどのような治療が行われるのか、その具体的な方法をご紹介します。
スケーリング・ルートプレーニング
軽度から中等度の歯周病ではまず、スケーリングとルートプレーニングという基本的な歯周治療が行われます。スケーリングでは、歯と歯ぐきの間にたまった歯石や歯垢を専用の器具で除去し、ルートプレーニングでは歯の根元を滑らかに整えます。
これらの処置によって歯周ポケットが浅くなったり炎症が抑えられたりすると、ぐらつきも軽減することがあります。
歯周外科治療
中等度から重度の歯周病の場合、歯周ポケットの深さや炎症の範囲によっては、歯ぐきを切開して歯根を直接露出させる歯周外科治療(フラップ手術)が必要になります。これにより、奥深くにたまった歯石や感染部分を徹底的に除去し、炎症の原因を取り除くことができます。
術後は歯肉の再付着が進み、歯のぐらつきが改善される場合もあります。
歯周組織再生療法
近年では、歯周病によって破壊された骨や歯周組織の再生を促す歯周組織再生療法も注目されています。エムドゲインやGTR(組織再生誘導法)といった方法を用いて、歯槽骨や歯根膜の回復を促進します。
ただし、この治療法は適応できる症例が限られており、すべての患者さまに効果があるわけではありません。
動揺した歯の固定
ぐらつきが強く、噛むたびに痛みや不快感が出る場合は、隣の歯と連結して動きを抑える歯の固定処置が行われることもあります。周囲の歯に負担を分散させることで症状を緩和し、治療効果を高めるサポートになります。
抜歯
歯周病が重度に進行し、骨の大部分が溶けていると歯を保存することが難しく、抜歯が選択される場合があります。歯を抜いた後はインプラントやブリッジ、入れ歯などで機能回復を図ることになります。
ただし、抜歯はあくまでも最終手段です。歯を抜かずに残すためにも、できるだけ早い段階で治療を受けるようにしましょう。
歯周病の進行を防ぐためにできること

歯周病は進行するまで症状に気づきにくいため、毎日のセルフケアや定期手な通院による予防が非常に重要です。歯のぐらつきが起こるほど進行する前に、日常生活の中で実践できる予防習慣を取り入れることが、健康な歯を保つために欠かせません。
この章では、歯周病の悪化を防ぐために意識したい習慣や具体的な対策についてご紹介します。
正しいブラッシングの実践
歯周病予防の基本は、毎日の歯磨きです。
ただし、やみくもにこするのではなく、歯と歯ぐきの境目を意識して丁寧に磨くことが大切です。歯ブラシは毛先が柔らかめのものを選び、軽い力で小刻みに動かすようにしましょう。
また、デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、歯と歯の間の汚れもしっかり取り除けます。
定期的な歯科検診とクリーニング
セルフケアでは落としきれない歯垢や歯石は、歯科医院での専門的なクリーニングによって除去する必要があります。特に歯石は、一度つくとセルフケアでは取れないため、3〜6か月ごとに定期検診を受けるのが理想的です。
早期発見・早期治療により、歯周病の進行を防ぐことができます。
生活習慣の見直し
食生活や喫煙習慣も歯周病に深く関わっています。糖分の多い食事や間食の頻度が高いと、歯垢がたまりやすくなり、歯周病菌の活動が活発になります。また、喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、免疫機能も低下させるため、歯周病のリスクを大きく高めます。
禁煙や栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
ストレス管理と全身の健康維持
見落とされがちですが、ストレスも歯周病の悪化に影響を与えることがあります。ストレスによって免疫力が低下すると炎症が広がりやすくなるため、規則正しい生活やリラクゼーションなどで心身の健康を保つことも予防策の一つです。
また、糖尿病などの持病がある方は、病気のコントロールも重要です。全身の病気と口腔内の健康は密接に関係しているため、口内環境だけにとらわれず、全身の健康に注意を払いましょう。
まとめ

歯がぐらつくという症状は、歯周病のサインである可能性が高く、決して見過ごしてはいけません。歯周病が進行すると歯を支える骨が破壊され、最終的には歯を失うこともあります。
しかし、早期に発見し、適切な治療を行えば、多くの場合は歯を残すことが可能です。また、治療と同時に日々の予防習慣を見直すことも、進行を食い止めるうえでは欠かせません。
今回ご紹介したように、正しいブラッシングや定期的な歯科検診、生活習慣の改善、ストレス管理など、実践できることは多くあります。もし歯がぐらぐらすると感じたら、自己判断せずに早めに受診しましょう。
歯周病治療を検討されている方は、長崎県諫早市にある歯医者「諫早ふじた歯科・矯正歯科」にお気軽にご相談ください。
————–
長崎県諫早市多良見町中里129-14
医療法人 夢昂会 諫早ふじた歯科・矯正歯科
電話番号 0957-43-2212
ネット予約
—————