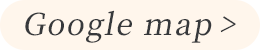目次
指しゃぶりは歯並びに悪影響がありますか?
はじめに
諫早ふじた歯科・矯正歯科の藤田です。今日はよくある質問の中から指しゃぶりに関してのお話です。
赤ちゃんや幼児にとって「指しゃぶり」は自然な行動のひとつです。眠たいときや安心したいときに親指をくわえる姿は、親御さんにとっても微笑ましい光景でしょう。しかし成長するにつれ、「このまま続けていて大丈夫なの?」「歯並びに悪影響はないの?」と不安を抱く方も少なくありません。
本記事では、指しゃぶりと歯並びの関係、いつまでなら大丈夫か、やめさせ方のポイントについて、歯科医の立場から詳しく解説します。

指しゃぶりはいつまでなら大丈夫?
乳児期の指しゃぶり
生後すぐから2歳くらいまでは、指しゃぶりは心の安定や入眠儀式の一環であり、無理にやめさせる必要はありません。乳児期の指しゃぶりは自然な発達過程の一部と考えられています。
3歳以降は注意が必要
多くの子どもは成長とともに自然に指しゃぶりをやめますが、3歳を過ぎても続いている場合は歯並びへの影響が出始める可能性があります。特に永久歯が生えてくる5歳〜6歳頃まで指しゃぶりを続けると、歯や顎の発達に大きな影響を与えることがあります。
指しゃぶりが歯並びに与える悪影響
1. 出っ歯(上顎前突)
長時間、指で前歯を押すことで上の前歯が前方に傾き、いわゆる「出っ歯」になりやすくなります。
2. 開咬(かいこう)
上下の前歯が噛み合わず、前歯の間に隙間ができる「開咬」も指しゃぶり特有の歯並びの乱れです。食べ物を噛み切りにくかったり、発音に影響が出る場合があります。
3. 受け口(反対咬合)
指しゃぶりによる舌や顎への圧力で、下の顎が前にずれる「受け口」になるケースもあります。
4. 顎の発育への影響
指が長時間口の中にあることで、顎の成長が左右不均衡になり、噛み合わせ全体に悪影響を及ぼす可能性もあります。

影響が出やすい条件
1日に長時間指しゃぶりをしている
強く吸う癖がある
就寝時も習慣化している
5歳を過ぎても続けている
このような場合は特に注意が必要です。
指しゃぶりをやめさせる方法
「やめなさい!」と叱っても逆効果になることが多いため、ポジティブなアプローチが大切です。
1. 成長に合わせた声かけ
「もうお姉さん(お兄さん)だから、指しゃぶり卒業できるね」と前向きに励ましましょう。
2. 手を使った遊びを増やす
ブロック遊びやお絵描きなど、手を使う遊びで自然に指を口から離す習慣を作ります。
3. 寝る前の安心アイテム
ぬいぐるみやお気に入りのタオルなどを持たせることで、指しゃぶりの代わりに安心感を得られる場合があります。
4. 爪に塗る苦味成分のある専用製品
どうしてもやめられない場合に、歯科で指導のもと使うことがあります。
歯科医院でできるサポート
もし歯並びへの影響が出始めている場合、歯科医院では以下のような対応が可能です。
定期的な経過観察(指しゃぶりの習慣が残っていても、歯や顎の発達を確認できます)
やめられない子へのカウンセリング
必要に応じたマウスピース型の装置で指しゃぶりの習慣を抑える
よくある質問(Q&A)
Q1. 指しゃぶりでついた歯並びの悪影響は治りますか?
→ 乳歯列の時期にやめれば、多くの場合自然に改善されます。ただし、永久歯に影響が出ている場合は矯正治療が必要になることがあります。
Q2. おしゃぶりは指しゃぶりより良いのですか?
→ 長期間の使用は同じように歯並びに影響することがありますが、コントロールしやすいため指しゃぶりよりやめさせやすい利点があります。
Q3. 何歳までにやめるべきですか?
→ 目安としては3歳頃まで。遅くとも5歳までにはやめることが望ましいです。
まとめ
指しゃぶりは乳児期には自然な行動であり、すぐに問題にはなりません。
しかし3歳を過ぎても続けると歯並びに悪影響が出る可能性があります。
出っ歯・開咬・受け口など、噛み合わせの乱れにつながることがあります。
やめさせ方は「叱る」のではなく「安心させる・代替行動を与える」ことがポイントです。
不安な場合は小児歯科で早めに相談するのがおすすめです。
当院でのサポートについて
諫早ふじた歯科・矯正歯科では、お子さまの指しゃぶりや歯並びに関するご相談を随時受け付けております。
お子さまの成長や性格に合わせたサポート方法をご提案し、必要に応じて矯正治療も行っております。
📞 お電話でのお問い合わせ:0957-43-2212
🌐 Web予約はこちら:ご予約ページ
お子さまの将来の健やかな歯並びのために、気になることがあればお気軽にご相談ください。