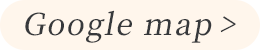こんにちは。長崎県諫早市にある歯医者「諫早ふじた歯科・矯正歯科」です。

「床矯正とは、どんな矯正なの?」「床矯正ができる年齢の目安は?」と疑問を持っている保護者の方も多いでしょう。お子さまの歯並びは将来の噛み合わせや見た目に影響するため、早めに対応したいと考える方は少なくありません。
この記事では、床矯正に関するメリット・注意点を中心に、適応年齢の目安まで分かりやすく整理しました。床矯正に興味がある保護者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
床矯正とは

床矯正は、取り外し可能な樹脂製のプレート(床)にネジやワイヤーを組み込み、少しずつ顎の幅を広げて歯が並ぶスペースを確保する小児向けの矯正法です。顎の成長に合わせて骨や歯槽骨の位置を調整することで、整った歯並びの土台を作ります。
装置は自宅で着脱できるためブラッシングを行いやすい反面、所定の装着時間を守る必要があります。年齢や骨格の状態によって適応や効果に差が出るので、まずは検査で成長段階や咬合の状態を確認して、治療方針を決めることが大切です。
床矯正のメリット

床矯正にはどのようなメリットがあるのか、気になった方も多いでしょう。床矯正のメリットは、以下のとおりです。
抜歯を避けられる可能性が高まる
床矯正は、顎や歯列の幅を広げることで永久歯が生えるスペースを確保する治療です。乳歯と永久歯が混在する時期に適切な拡大を行うと、将来的に歯を抜かずに並べられる確率が上がります。
痛みを抑えて進められる
床矯正は、顎の成長を利用して段階的に歯列の拡大を実施する治療です。そのため、強い力をかけて歯を大きく動かす矯正に比べて痛みが抑えられるとされています。
装置で少しずつ歯列にスペースを作るので、違和感や歯の圧迫感が軽く済むケースが多く、日常生活への影響を抑えられるでしょう。もちろん個人差はあるため、お子さまが強い痛みや違和感を訴える場合は、かかりつけの歯科クリニックに相談して調整を受けてください。
自分で取り外せるため負担が少ない
床矯正の装置はお子さま自身で取り外しができるため、食事や学校行事など生活シーンに合わせて外せます。就寝中や日中の指定時間に装着するルールを守る必要はありますが、固定式装置のように常時装着し続けるわけではありません。
そのため、見た目のストレスや口内の不快感を軽減しやすくなります。装着時間を確保できるよう保護者の方や本人と歯科クリニックが連携して管理しなければならない点に注意しましょう。
ブラッシングがしやすく虫歯予防につながる
ブラッシング時に装置を外して隅々まで清掃できるため、食べかすや歯垢が装置の隙間に残りにくくなります。固定式の矯正装置に比べて口内の清潔を保ちやすく、歯ぐきの健康を守りつつ虫歯の発生リスクを下げられます。
食事制限が少ない
固定式の装置を使用する矯正では、硬いものや粘着性のある食品を避けなければならないことがあります。
しかし、床矯正の装置は食事の際に外せるため、食べ物の制限がほとんどありません。好きなものを食べやすく、食事中の不便さやストレスを軽減できます。装置を外した後の保管場所や装着時間の管理は重要ですので、取り扱い方法を守って正しく使用してください。
床矯正の注意点

どのような治療法にも、メリットだけでなく注意すべき点があります。ここでは、床矯正で注意するポイントを確認しましょう。
装着時間を守らなければ効果が出にくい
床矯正は取り外し可能な点がメリットですが、治療効果を得るには決められた装着時間を確保する必要があります。一般的には1日12〜14時間の装着が目安となり、これを大きく下回ると顎や歯列の拡大が進まず、予定した治療効果が得られなくなります。
特に、幼児期のお子さまは自己管理が難しいため、保護者の方による着脱の管理や歯科クリニックでの定期的なチェックが重要です。装着時間が極端に不足すると、装置の再製作や治療期間の延長につながるため、ご家族で装置の使用ルールを決めておくと良いでしょう。
慣れるまで異物感が出ることがある
床矯正の装置を装着した直後は、口内に違和感を覚えやすく、舌の動きが制限されることで発音がしにくく感じるお子さまが多いです。通常は数日から2週間ほどで徐々に慣れて会話や飲食に支障がなくなりますが、中にはストレスを強く感じるお子さまもいます。
発音練習や短時間ずつ装着時間を延ばすなど段階的な適応方法が有効で、問題が続く場合は早めに歯科クリニックで調整や対策を相談してください。
細かな歯の調整に別治療が必要な場合がある
床矯正は、主に歯列全体の幅を広げてスペースを作る治療です。個々の歯を精密に移動して咬合を完璧に整えるのは難しいです。
そのため、歯列拡大でスペースを確保した後に、マウスピース矯正やワイヤー矯正などで歯の向きや位置を細かく調整する二段階の治療計画を立てることが多くあります。治療開始時に将来の流れを歯科医院で確認しておくとよいでしょう。
後戻りが発生することがある
矯正治療終了後でも、顎の成長や口周りの筋肉の使い方、指しゃぶりや舌の癖などによって歯列が元の位置へ戻る後戻りが起こることがあります。これを防ぐには、保定装置の使用や定期検診が欠かせません。
保定期間には個人差がありますが、担当の歯科クリニックで指示された期間・方法を守ることで安定性を高められます。万が一後戻りが見られた場合は、再治療や別の矯正方法の検討が必要になるため注意しましょう。
床矯正の適応年齢

床矯正は5~12歳ごろに行うケースが多いです。
しかし、年齢だけで決めることはありません。顎の成長段階と乳歯・永久歯の生え変わり状況を重視して適応を判断します。幼児期から小学生の成長期に最も効果が出やすいとされていますが、骨の発達具合や咬合状態によって開始する時期は大きく変動します。
乳歯と永久歯が混在する7〜9歳ごろは、顎の成長が活発で歯列を拡大しやすいため床矯正の効果を得やすい時期とされています。この時期に十分なスペースを確保できれば、永久歯が自然に並ぶ可能性が高まり、咬合の基本的なバランスを整えやすくなります。
顎のスペースを広げて永久歯が自然に並べば、将来的な矯正治療が不要になる可能性もあります。
床矯正の費用の目安

床矯正にかかる総額は、歯科クリニックや装置の種類、治療の難易度で幅が出ます。一般的には、20万円前後から50万円程度が目安とされています。
10万円台から受けられる場合や、装置や調整回数が増えて総額が50万円を超えるケースもあるため、事前に見積もりを確認しておきましょう。装着時間が不足して治療期間が延びた場合は、追加の費用が発生するケースが多いです。
まとめ

床矯正は、顎の成長を利用して歯並びのスペースを確保する治療です。顎のスペースを確保できれば、将来的に矯正治療が不要になったり、矯正をする場合でも抜歯を避けられたりする効果が期待できます。
取り外し可能な装置を使うため、ブラッシングがしやすく、食事制限も少ないのが特徴です。
ただし、決められた装着時間を守らなければ効果は出にくく、慣れるまでは発音や装着感に違和感が出ることがあります。
また、歯を移動させる治療ではないので、精密な歯の移動には追加の治療が必要になることがある点を理解しておきましょう。後戻り防止には、治療後の保定も必要です。
矯正治療の開始時期や計画は、顎の発育状態や歯並びによって異なるため、気になる場合は歯科クリニックで早めに相談してみましょう。
床矯正を検討されている方は、長崎県諫早市にある歯医者「諫早ふじた歯科・矯正歯科」にお気軽にご相談ください。
————–
長崎県諫早市多良見町中里129-14
医療法人 夢昂会 諫早ふじた歯科・矯正歯科
電話番号 0957-43-2212
—————