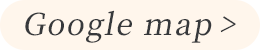親知らず
「親知らずが痛い。頬が腫れている。歯医者に行くべきか?」
親知らずの悩みを持つ方へ、親知らずのことを詳しく解説します。
親知らずは虫歯や歯周病といった口の中のトラブルが痛みを引き起こしている可能性があります。
親知らずをそのまま放置しておくと、思いがけない大きな口に病気に発展してしまう可能性もあるので早めのケアが必要です。

親知らずはなぜ痛いのか
親知らずはなぜ痛いのか?それは「親知らずが生えることによって生まれる歯や口のトラブル」が原因となっているからです。 もちろん、親知らずが周りの骨や歯や歯茎などを圧迫するからと言った理由もあるのですがそれはごくまれです。 親知らずの痛みの原因を順番に解説していきます。
虫歯、歯周病
親知らずは綺麗にまっすぐ生えることは少なく、斜めに生えたり曲がって生えたりするので歯磨きがしづらくなり、虫歯や歯周病になりやすくなります まっすぐ生えてたとしても、奥歯のさらに奥の場所に入るので、歯磨きがしづらいものです。 親知らずだけならいいのですが、親知らずの手前にある奥歯と接着している部分はとても磨きにくく、虫歯ができやすくなります。 親知らず周辺の位置に痛みを感じた場合はすぐに歯医者に行くことをお勧めします。
智歯周囲炎
智歯周囲炎も歯磨きがうまくできないことで起きる炎症です。 親知らずの位置だけではなく、顎全体が痛みます。 少しでも智歯周囲炎だと思われる症状がある場合はすぐに歯医者に行きましょう。
歯性感染症
歯性感染症は、虫歯や歯周病や智歯周囲炎などの炎症が歯茎や筋肉や骨にまで侵入することで起きる様々な疾患です。 歯性感染症には、主に2つのものがあります。
顎骨骨膜炎
虫歯菌などが顎の骨に感染して起こる感染症です。顎だけではなく顔全体が腫れます。心臓の鼓動と一緒にずきずきと痛みます。
化膿性リンパ節炎
虫歯菌などがリンパに感染し、リンパ節が腫れます。熱が出る場合も。 歯性感染症は、抗生物質で炎症を抑えます。 しかし抗生物質で炎症を抑えたところでその場しのぎの治療でしかなく、親知らずを抜かないと根本的な解決にはなりません。
抜歯したほうがいい場合
親知らずは必ず抜いたほうがいいわけではなく、正直人それぞれとしか言えません。 ただ一言で親知らずと言っても、状況は様々で抜いた方がよい場合と抜かなくてもよい場合と分けられます。 どういった状況で分けられるか解説していきたいと思います。
親知らずとはそもそも何?どこの歯?
親知らずとは、正式名称は「第三大臼歯」「智歯」と呼ばれる歯のことです。 基本的に人間の歯は中切歯・側切歯・犬歯・第一小臼歯・第二小臼歯・第一大臼歯・第二大臼歯の7本で構成されています。 親知らずは8番目の歯で、第二大臼歯の後ろに生えます。個人差は大きいですが、だいたい20歳前後に口の中に見えてきます。 昔は寿命も短く50歳くらいで亡くなる人も多かったようです、親知らずが生えてくる頃には両親が他界していることから、「親知らず」と呼ばれるようになったようです。親知らずが生える位置は歯列の一番奥になります。 では、次に親知らずは抜くべきか、説明したいと思います。 ただし、実際に処置する時は事前に担当の歯科医師をよく相談をし抜くかどうかの判断をしてください。

親知らずを抜いた方がよい場合
① 親知らずが横向き(水平)に生えている場合
親知らずは顎の骨のスペースの関係上横向きに生えてくる事があります。横向きに生えてくると、噛み合わせに参加することはありません。 また、歯が完全に歯茎の上に出ることもないため、半埋伏と言われる状態になり歯の頭の部分が半分歯茎の中、半分歯茎の上という非常に清掃性が悪くなります。 歯の周囲の歯茎が腫れやすく、ひどいときは顔も腫れてくる事があるため抜歯したほうがよいと思います。
② 上下で噛み合っていない場合
歯は上下で噛み合ってはじめて機能します。噛み合っていない歯はただ磨き残しや歯石・プラークの温床になるだけです。おいておくメリットとしては、移植する歯として使えることもありますが、稀です。 磨きにくい位置に歯を残すことで口腔内の細菌量が増えるデメリットの方が大きいと考え抜歯を勧めます。
③ 矯正治療をしている場合
矯正治療により、理想的な歯並びになった後、親知らずの萌出により、歯並びが崩れてしまうことがあります。矯正が必要な方は元々顎に親知らずの生えるスペースがない人が多いと思います。矯正前、矯正後に生えてくる可能性がある場合は矯正後早い段階で抜歯しておいた方がよいでしょう。
④ 大きな虫歯になっている場合
すでに親知らずが大きな虫歯になっている場合も抜歯をすすめます。 何故かというと、親知らずは顎の一番奥に生えているため虫歯の治療が非常に困難で、手前の歯と同様のレベルで治療できるかというと難しいというのが事実です。 処置を受ける患者様としても親知らずは治療するより抜かれる方が楽なことが多いと思います。
親知らずを抜かなくてもよい場合
① 歯磨きが非常に上手で親知らずがまっすぐに生えている場合
② 顎が非常に大きく、親知らずの生えるスペースが十分にある場合
③ 上下の親知らずがしっかりと噛み合っており、噛み合わせに参加している場合
親知らずを抜く時の注意点
上の親知らずでは、上顎洞への歯の迷入や親知らずの後ろ側の骨の骨折による出血や神経の損傷には十分注意が必要です。
下の親知らずを抜く場合は特に注意が必要です。
というのも、下顎には下顎管と呼ばれる神経と血管のは入った管が通っています。
親知らずの根がこの下顎管と接していたり、巻き込んでいたりすると抜歯することで神経や血管を損傷しひどい痛みや出血、神経の麻痺を起すリスクがあります。
現在は保険内でもこの下顎管と親知らずの位置を調べるCT撮影が可能です。
痛かったら抜歯をしたほうがいいのは理解いただけると思いますが、痛みがない場合でも抜歯をしたほうがいいケースもあります。

抜歯後のケア
親知らずの抜歯は、麻酔をかけますので痛みはほとんどありません。 しかし、抜歯が終了して麻酔が薄れてくるとじわじわと痛みがでてきます。 顎の骨を削ったり、歯茎を切開して抜歯した場合は、1週間痛みが継続する場合もあります。 痛み止めや抗炎症剤は処方しますが、痛みがゼロになることはありません。 激しく痛む場合は、別の薬を試したり、アイシングをするなど様々な方法で痛みを和らげることもできます。
親知らず Q&A
親知らずとはどんな歯ですか?
親知らずは、奥歯の一番奥に生えてくる第3大臼歯で、通常18歳〜25歳頃に生えてきます。上下左右で最大4本ありますが、すべて生えそろわない人も多く、生まれつき無いケースもあります。スペースが足りずに斜めや横向きに生えてくることもあり、他の歯や歯ぐきに悪影響を与える原因になることもあります。
親知らずは必ず抜く必要がありますか?
すべての親知らずを抜く必要はありません。正しい方向に生え、周囲の歯に悪影響がなければそのまま残しておくこともあります。ただし、斜めに生えていたり、手前の歯を圧迫している場合、虫歯や歯周病のリスクが高まるため、抜歯が推奨されます。痛みや腫れの兆候がある場合は早めの診察が重要です。
抜歯するタイミングはいつが最適ですか?
親知らずの抜歯は、痛みや腫れが出る前の予防的な段階で行うのが理想です。特に若い時期(10代後半〜20代前半)は骨が柔らかく、治癒が早いため抜歯に適しています。痛みが出てからでは炎症が強く、抜歯が困難になることもあるため、早期の検査と判断が大切です。
親知らずの抜歯は痛いですか?
抜歯は局所麻酔をして行うため、処置中の痛みはほとんどありません。処置後には腫れや軽い痛みが出ることがありますが、痛み止めでコントロール可能です。抜歯後数日は安静にし、冷やす・刺激のある食事を避けると、回復がスムーズになります。医師の指示を守ることが大切です。
抜歯後の腫れや痛みはどれくらい続きますか?
一般的には、抜歯後1〜2日は腫れや痛みがピークとなり、その後徐々に落ち着いていきます。完全に腫れが引くまでは1週間ほどかかることもあります。処方された痛み止めを服用し、無理せず過ごすことが重要です。腫れが長引いたり、強い痛みが続く場合は、早めに再診を受けましょう。
親知らずを放置するとどうなりますか?
放置すると、手前の歯を押して歯並びが悪くなったり、歯と歯の隙間に汚れがたまり虫歯や歯周病を引き起こすリスクがあります。また、膿がたまる「智歯周囲炎」や顎の腫れ・口が開きにくくなる症状に発展することもあります。異変を感じたら早めの検査と処置が推奨されます。
親知らずが虫歯になった場合どうすればいい?
親知らずが虫歯になると治療が難しいケースが多く、特に斜めや横向きに生えている場合は器具が届きづらく、治療の効果も限定的です。そのため、多くの場合は虫歯治療よりも抜歯が選択されます。他の歯に悪影響を及ぼす前に、早めの対応が必要です。
親知らずの抜歯にはどのくらい時間がかかりますか?
抜歯時間は歯の状態によって異なりますが、簡単なケースであれば10〜15分ほどで終わります。埋まっている親知らずや、骨に近接している場合は30分〜1時間程度かかることもあります。術後の説明や麻酔の確認を含めると、全体で1時間程度を見ておくとよいでしょう。
親知らずが生えてきているかどうかはどうやって分かる?
自覚症状としては、奥歯のあたりの違和感や痛み、歯ぐきの腫れがありますが、正確な位置や向きはレントゲン(パノラマX線)撮影で確認します。肉眼では見えなくても、歯ぐきの下に横向きで埋まっている場合もあるため、気になる症状があれば歯科医院で検査を受けましょう。
親知らずの抜歯後に気をつけることは?
抜歯当日は激しい運動や長風呂を避け、出血が続く場合はガーゼをしっかり噛んで圧迫止血します。また、強いうがいは血餅(かさぶた)を取ってしまう恐れがあるため注意が必要です。食事はやわらかいものを選び、刺激物は避けてください。喫煙やアルコールも控えることで、治癒が早まります。